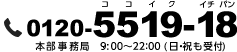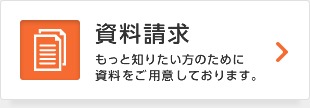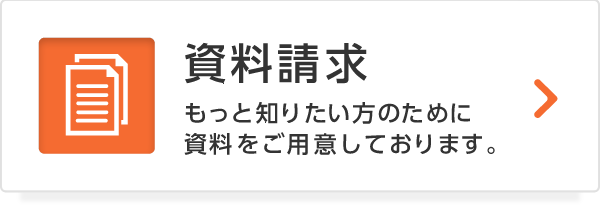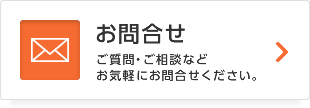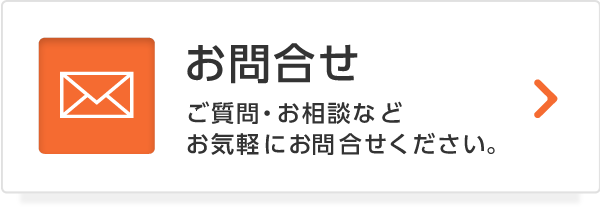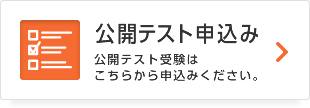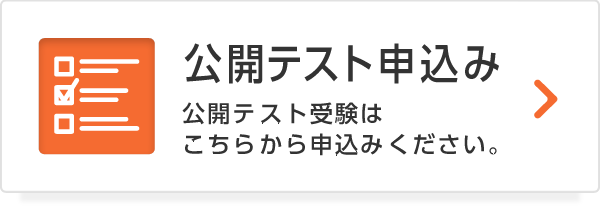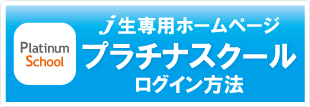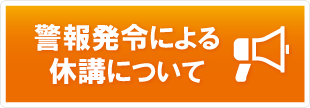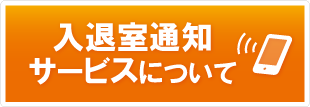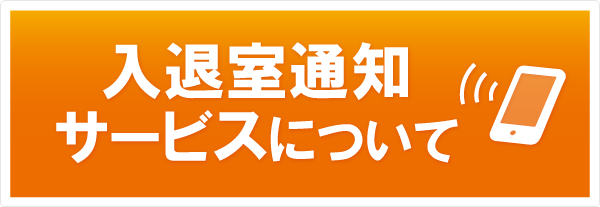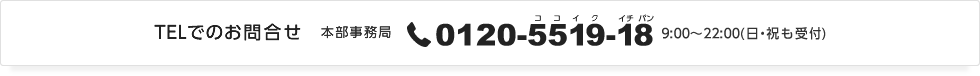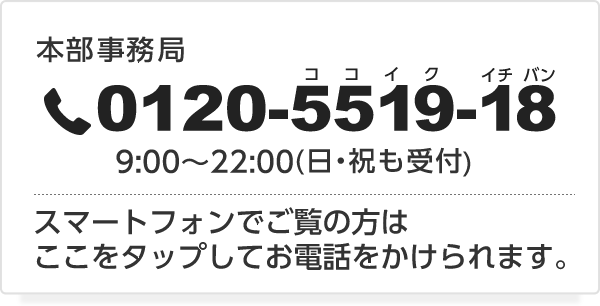2025年春 大学合格体験記
-
京都大学 医学部 人間健康科学科合格 Y・Aさん
私は第一志望の大学に合格することができました。今まで頑張ってきて良かったと心から思います。塾に行くと頑張れる環境がありました。たくさんの同級生が静かに勉強している姿を見ると、自然と自分も集中して取り組めました。他の人が頑張っているから、自分も頑張ろうと思うことができ、周囲の受験生から刺激を受けることで、自分を高められました。また、受験校決定に向けては、勇気と自信を持つことが大切だと思います。高校3年生になった時、実はまだ志望校が定まっていませんでした。「私なんかが…」という思いがあり、高い目標を持てていませんでした。しかし、学校の先生、塾の先生、親をはじめ、たくさんの人に背中を押していただき、「京都大学を受験する」と決められました。そして、強い意志を持って勉強に取り組み、数々のサポートのおかげで受験を乗り越えることができました。これからの大学生活、勉強も遊びも、全力で楽しんでいきます。
-
大阪大学人間科学部合格 I・Nさん
僕の高校3年間を一言で表すと「猪突猛進」だと思います。学校行事などの課外活動では、つくば研修でリーダーとして参加したり、文化祭では総合司会を務めたりしました。部活動では陸上部のキャプテンを務め、3年の11月の県駅伝まで走り続けました。このような経験は受験勉強の中でも大いに役立ち、自信や学びへの意欲、最後まで諦めない忍耐力、本番の緊張に動揺しない力に繋がったと思います。そして、最も大切だと思うのが、目の前のことに一生懸命になることです。定期テストにしても普段の小テストにしても、目の前の目標に向けて全力を尽くせば、必ず実力がついてきます。僕は、1年や2年のうちから阪大をめざしていたわけではなく、定期テストや課題など、全科目で手を抜かなかったことで力をつけることができました。これからの人生においても、目の前のことに全力で打ち込むとともに、それができる環境に身を置けるように努力していきたいと思います。
-
九州大学 医学部 保健学科合格 A・Kさん
私が受験勉強を通して一番大切だと感じたことは、「願書を出す時まで目標を下げない」ということです。本番の共通テストでは思うような点数を取ることができなかったのですが、これまで医学部という高い目標に向けて努力し続けていたので、最終的に旧帝大に合格できました。現役生は、共通テスト直前でも得点を大幅に伸ばすことができるので、最後まで高みをめざして頑張ることが大事です。また、私がやってきて良かったと思うことは、高2生の秋から少しでもいいので受験勉強を始めるということと、高3生になったと同時に本気を出して取り組むということです。そして、苦労したこととしては、共通テストと二次試験で、得意科目と不得意科目が逆転したことです。やはり最後には、成績は勉強時間に比例するので、バランス良く取り組むのが得策です。。
-
神戸大学 国際人間学部合格 U・Rさん
私は野球部に所属しており、7月中旬まで部活がありました。周囲が本格的に受験勉強に取り組んでいる中、自分は取り残されている気がして内心は焦っていました。そんな私が高校3年間における勉強で心掛けていたことを2つお伝えします。1つ目は「勉強をルーティーン化する」こと。部活後、18時半頃に学校を出てマナビスへ直行するというのを習慣づけることで、勉強の取り掛かりがあまり苦になりませんでした。2つ目は「一つひとつの模試を大切にする」こと。私は共通テストの化学が苦手で30点前半を叩き出したこともありました。化学が得意な友人は、模試で間違えた問題を何度も復習していたので、私も実践するようにすると、次の模試で70点と、得点を大幅に伸ばすことができました。これから受験生になる皆さんに参考になれば嬉しいです。
-
筑波大学 理工学群合格O・Kさん
私は、マナビスに通う前までは勉強意欲が湧かず、宿題のみに取り組む日々が続いていました。このままではいけないと思いマナビスへ通うようになると、いつでも講座を受けられたり、質問ができたり、自分のペースで進められるところが自分に合っていて、予習・復習がスムーズにでき、自然と勉強習慣を身につけられるようになりました。受講する講座は、アドバイザーの方と相談しながら、その時々で自分に必要なカリキュラムを組むことができたのも良かったです。特に、私は英語が苦手で読解問題に苦戦していましたが、基本に戻り、文法と語法の学習を徹底的に行ったことで、英文が読めるようになりました。勉強を習慣化できるようにすること、不安な点はアドバイザーにたずねることで、私は受験を乗り越えることができました。
-
神戸大学 工学部 O・Fさん
私は自分一人で勉強すると、どうしても得意科目ばかりしてしまうので、ジェイの個別指導に通っていました。当初は、まだ受験なんて先の話で高3生になってから考えれば大丈夫だと思っていました。しかし、そう思っていたことが大間違いであるということに、参考書を進めていく中で気づきました。神戸大学の過去問に目を通してみるも全く歯が立たず、解答方法を覚えればできるという考えも間違っていました。その解答方法をしっかりと活用するということ、つまりはアウトプットをきちんとしないと問題は解けません。さらには、そのアウトプットの時間が勉強の中で最も大切で、最も時間がかかることでした。だからこそ、受験は遠い未来の話ではなく、すぐそこにあると危機感を持って、なるべく早くから対策するのがとても大切です。
-
広島大学 文学部 F・Yさん
受験は、一人で勉強を続けることがとても辛く、苦しい道のりだと思います。「受験は団体戦」と言われることがありますが、受験を終えて振り返ると、やはりコミュニケーションを取り合うことが、自分にとって勉強面や精神面でプラスになったと実感しています。そして、受験勉強において苦手な科目に関しては、自分から対策をしようとしない限り、時間が解決してくれることはありません。また、自分なりに対策をしたつもりでも、なかなか結果に反映されないことも多いです。得意科目の方が勉強が楽しく、時間が過ぎてしまいますが、勉強に取り掛かる際は、苦手科目→得意科目の順で行うようにすると、やり残しが減ると思います。
-
岡山大学 医学部 看護学科 A・Aさん
私は、受験勉強においては量より質を重視すべきだと考えています。私が良かったと思う学習方法は「模試ノート」を作ることです。マナビスには多くの講座や問題集があるので、それを利用して入試傾向に慣れることができます。暗記系科目で間違えたものや選択肢の中でわからないものは、全てノートに書いて、寝る前に見返すようにしていました。「自分だけの苦手」が詰まったノートは、弱点克服に役立ち、受験当日もお守りになりました。そして、諦めることなく勉強を続けるためには、自分の息抜きを見つけ、勉強と休みのメリハリをつけることです。友人と励まし合えばきっと乗り越えられます。
-
兵庫県立大学 環境人間学部 K・Hさん
私がマナビスに通って良かったと思うことは、苦手な部分や間違えやすい部分を自分で把握できるようになったことです。「アドバイスタイム」では、自分で間違えた部分を説明するので、どこで、どのように間違えたかが理解できるようになりました。そして、アシスタントアドバイザーを含む講師の皆さんは、勉強面での身近な先生として質問がしやすく、いつも寄り添ってくださる存在でした。最後に、同じ大学や学部をめざしている後輩の皆さんへ。環境人間学部は、総合問題です。各教科にどれだけ時間をかけるか、どの教科から取り掛かるか決めておく必要があります。また、学部によっては必要な受験資格もあるので事前によく調べることをおすすめします。
-
岡山大学 工学部 S・Sさん
私が受験を通して思うことは、何事においても有効に活用するも、しないも自分次第ということです。私は高3になるまではあまり勉強に身が入らず、せっかく講座を受けていても知識をほとんど身につけられていませんでした。そして、受験生としての焦りから勉強に取り掛かった時、きちんと講座を受講して、わかりやすさに感動し、今までの自分の態度を非常に後悔しました。勉強嫌いだった自分が勉強を習慣づけられるようになり、苦手だった英語を好きになるきっかけとなったのはマナビスの講座でした。この教訓を糧に、今後も何事にも自分が主体となって行動していこうと思います。